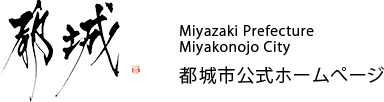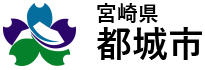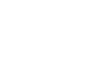本文
【事業終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)についてお知らせします
10月31日の申請期限をもって、本給付金の受付は締め切りました
給付金の概要や手続き方法等についてお知らせします。
本給付金の対象と見込まれる方に対し、8月の中旬から下旬にかけて文書を送付いたしました。ご自身が対象と思われるにもかかわらず通知が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
不足額給付の制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
給付対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が都城市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当諸調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、留意ください。
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万を超える者
文書発送
本給付金の対象と見込まれる方に対し、8月中旬から下旬にかけて文書を送付しました。
ただし、令和6年度の個人住民税課税自治体が本市ではない方(令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に本市に転入された方など)のうち、課税状況や支給条件を満たすかどうか等を把握できない場合は、本市から書類をお送りすることができず、対象者本人様からの申請が必要となる可能性があります。ご自身が対象と思われるにもかかわらず文書が届かない場合は、コールセンターまで問い合わせください。
手続き方法等
(1)支給通知書兼振込通知書が届いた方【原則手続き不要】
公金受取口座もしくは当初調整給付受給口座を把握できた不足額給付1の対象と見込まれる方には、本市より「都城市物価高騰重点支援給付金(調整給付金不足額給付分)支給通知書兼振込通知書」をお送りしております。封書が届きましたら、通知書の記載内容を必ずご確認ください。
原則、お手続きが不要です。書類に記載のある口座(公金受取口座もしくは当初調整給付受給口座)へ9月18日(木曜日)に給付金を振込みます。
給付の辞退を希望される場合や記載された当該口座以外の口座へ振込先の変更を希望される場合は、手続きが必要となりますので、9月9日(火曜日)までにコールセンターへ連絡ください。
(2)確認書(黄緑色の用紙)が届いた方【手続き必要】
口座情報が把握できなかった不足額給付1の対象と見込まれる方には、本市より「都城市物価高騰重点支援給付金(調整給付金不足額給付分)支給確認書」を送付しています。封書が届きましたら、確認書の記載内容を必ず確認ください。
給付金の受給には、確認書の返送が必要です。確認書に必要事項を記入し、以下の提出書類を添付して、10月31日(金曜日)までに同封の返信用封筒で申請してください。
なお、オンライン申請も可能です。
オンライン申請であれば、処理時間の短縮が可能であるため、より早く手続きが完了し、支給を行うことができます。
同封のチラシを確認いただき、ぜひ活用ください。
提出書類
- 確認書(黄緑色の用紙)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)のコピーなど)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
注意事項
- 返送前に必要事項の記入漏れがないか再度確認ください。
- 提出期限までに返送がない場合および返送した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、受給を辞退したものとみなしますので、早めに返送ください。
- 振込予定日については、市が書類を受理してから約4週間が目安となっています。(受付件数や記入漏れ等の書類不備によって前後します。)
(3)申請書(水色の用紙)が届いた方【手続き必要】
課税資料等をもとに不足額給付2の支給要件を全て満たす可能性がある方には、本市より「都城市物価高騰重点支援給付金(調整給付金不足額給付分)専従者等申請書」を送付しています。封書が届きましたら、申請書の記載内容を必ず確認ください。
給付金の受給には、申請書の返送が必要です。不足額給付2の支給要件を全て満たす場合は、誓約・確認事項に誓約の上、申請書に必要事項を記入し、以下の提出書類を添付して、10月31日(金曜日)までに同封の返信用封筒で申請してください。
提出書類
- 申請書(水色の用紙)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)のコピーなど)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
申請書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
注意事項
- 返送前に必要事項の記入漏れがないか再度確認ください。
- 提出期限までに返送がない場合及び返送した申請書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、受給を辞退したものとみなしますので、早めに返送ください。
- 申請書の提出後、本市にて審査の上、支給要件に該当する場合は、記入いただいた現住所に支給確認通知書兼振込通知書を送付します。一方、支給要件を満たさないと判明した場合は、却下通知書を送付します。振込予定日については、支給確認通知書兼振込通知書に記載しますが、制度が複雑で審査項目が多いため、市が書類を受理してから4週間以上経過する場合があります。(受付件数や記入漏れ等の書類不備によって前後します。)
給付金を装った詐欺などに注意ください
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡ください。