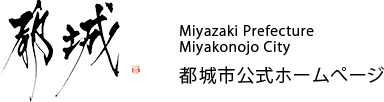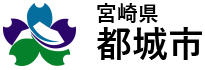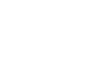本文
令和7年度特定健康診査および特定保健指導を実施しています
特定健康診査(特定健診)は、生活習慣病の前ぶれであるメタボリックシンドローム(メタボ)に着目した健診です。生活習慣病を防ぐため、年に1回特定健診を受診して自分の体の状態に気付き、健康づくりに役立てましょう。
対象者
国民健康保険加入者のうち40歳~74歳の人(昭和25年6月3日~昭和61年3月31日生まれ)
ただし、健診期間中に75歳の誕生日を迎える人は、誕生日前日まで特定健康診査、誕生日以降は後期高齢者健康診査です。健診内容は同じです。
実施期間
個別健診
令和7年6月2日(月曜日)~12月27日(土曜日)
集団健診
- 令和7年8月31日(日曜日)
- 令和7年9月26日(金曜日)
- 令和7年10月26日(日曜日)
- 令和7年11月14日(金曜日)
- 令和7年12月13日(土曜日)
- 令和8年1月17日(土曜日)
- 令和8年2月8日(日曜日)
実施場所
個別健診
個別健診は、次のファイルに記載する医療機関で受けることができます。
令和7年度特定健康診査実施医療機関 [PDFファイル/156KB](令和7年4月1日時点)
集団健診
集団健診は、下記会場で受けることができます。
- 令和7年8月31日(日曜日)都城市コミュニティセンター
- 令和7年9月26日(金曜日)沖水地区公民館
- 令和7年10月26日(日曜日)祝吉地区公民館
- 令和7年11月14日(金曜日)高崎福祉保健センター
- 令和7年12月13日(土曜日)五十市地区公民館
- 令和8年1月17日(土曜日)都城保健所
- 令和8年2月8日(日曜日)都城市コミュニティセンター
料金
無料
健診内容
基本項目
問診、身体計測、診察、血圧測定、血液検査、尿検査
詳細健診(前年度・今年度の健診結果で該当する人)
心電図検査、眼底検査
受診方法
- 健康診査受診券・問診票
- マイナ保険証又は資格確認書
を医療機関の受付に提示ください。
※問診票は記入の上、提示ください
※午前中に受診する人は朝食を摂らずに、午後から受診する人は昼食を摂らずに健診を受けてください
予約方法
個別健診
個別健診を受ける場合、原則予約不要ですが、一部要予約、かかりつけの方のみの医療機関があります。
令和7年度特定健康診査実施医療機関 [PDFファイル/156KB]で確認ください。
集団健診
集団健診を受ける場合は、事前予約が必要です。
インターネット予約<外部リンク>を利用するか、健康課へ予約ください。
注意事項
- 施設入所者、6カ月以上入院している人、および国民健康保険の人間ドックを受ける人は、特定健診は受診できません。
- 国民健康保険加入者以外の人は、各健康保険の保険者(社会保険、健保組合など)がそれぞれ健診を実施します。詳しくは、加入している健康保険組合に問い合わせください。
- 特定健康診査は、普段血液検査をしている人(治療中の人など)も対象となります。受診する際はかかりつけ医に相談ください。
- 市の健康診査を無料で受診できるのは、年度内に1回です。2回以上受診した場合の費用は、自己負担です。
- 体調に不安がある場合は、かかりつけ医などに相談のうえ受診日の変更など検討しましょう。
マイナポータル上で健診結果が閲覧できます
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、令和2年度以降の特定健診結果をマイナポータル上で閲覧できるようになりました(令和3年10月運用開始)。ぜひ、健康管理に役立ててください。
※受診した健診機関のデータ処理状況により、健診情報の登録が遅れることがありますので了承ください
詳しくは次の外部リンクを参照ください。
- デジタル庁マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」マイナポータル(外部リンク)<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省(外部リンク)<外部リンク>
生活習慣病にならないために、特定保健指導を活用ください
特定保健指導では、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して、医師や保健師や管理栄養士などが、対象者一人一人の状況に合わせた生活習慣を見直すためのサポートをします。特定保健指導には、リスク(高血圧、脂質異常症、高血糖や耐糖能異常、喫煙歴)の程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。
特定保健指導の対象となる人
特定保健指導は、国の指針に基づき、血圧や血糖、脂質の内服治療を受けていない人で、次の対象の基準1、2に該当する人に実施しています。
対象の基準1
- 腹囲が男性85センチメートル以上、女性90センチメートル以上 または
- BMI(体格指数:体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル))が25以上
対象の基準2
血糖高値
- 空腹時血糖が100ミリグラム/デシリットル以上 または
- Hba1c(ヘモグロビンエーワンシー)(Ngsp値)が5.6%以上
脂質異常
- 中性脂肪が150ミリグラム/デシリットル以上 または
- 随時中性脂肪が175ミリグラム/デシリットル以上 または
- Hdlコレステロールが40ミリグラム/デシリットル未満
血圧高値
- 収縮期血圧が130ミリメートルHg以上 または
- 拡張期血圧が85ミリメートルHg以上
特定保健指導に該当しない人にも、検査値に応じて保健指導を行っています
特定保健指導に該当しない人で、血圧や血糖、中性脂肪、コレステロール、腎機能などの数値が悪化している場合には、個別に保健指導や病院への受診をお薦めしています。
都城市は透析の人が多く、透析の原因疾患であるCKD(慢性腎臓病)も特定健診で早期発見ができます。
CKD(慢性腎臓病)
近年急増しているCKD(慢性腎臓病)は、そのままにしていると、知らず知らずのうちに腎機能が低下し、いつのまにか透析が必要な段階に悪化していることも少なくありません。
透析導入の原因として最も多いのは糖尿病性腎症で、全体の4割を占めています。
CKDになりやすい人の特徴
- 家族に腎臓病や人工透析を受けている人がいる。
- 学校の検診などで尿検査(蛋白、潜血)で異常を指摘されたことがある。
- 急性腎不全やIgA腎症、腎盂腎炎(じんうじんえん)などの腎疾患を患ったことがある。
- 片方しか腎臓がない、萎縮しているなど、腎臓の形態異常を指摘されたことがある。
- 膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群など)、感染症(慢性扁桃炎、溶連菌感染症など)、尿路結石、前立腺肥大などの泌尿器系の病気がある。
- 痛み止めを長期間飲んでいる、サプリメントをよく飲んでいる。
- 生まれた時の体重が2500グラム未満(未熟児)だった。
- 妊娠高血圧症候群や妊娠中にたんぱく尿が出ていた。(女性の場合)
腎臓を傷めない生活のポイント
- 塩分の摂りすぎに気をつけましょう(6グラム未満/日)
- 肥満を解消しましょう。
- 健診などで、血圧や血糖、コレステロールなどの数値が高かった場合は、基準値に近づけるように生活習慣を見直しましょう。
- 必要な薬以外は飲まないようにしましょう。
- 禁煙、アルコールの適正摂取に努めましょう。
- 排尿をがまんしないようにしましょう。
- ウォーキング程度の適度な運動をしましょう。
- 風邪などの感染症にかからないように予防しましょう。
- 睡眠を十分にとり、ストレスをためないようにしましょう。