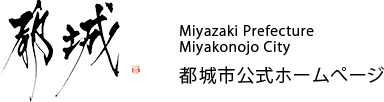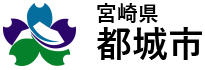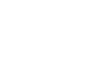本文
児童手当を支給しています
児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として、支給される手当です。
お知らせ
支給対象
日本国内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方
- 施設入所または里親委託の児童は、施設の設置者(理事長など)または里親へ支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)にも支給されます。
- 離婚または離婚調停中(裁判所発行の書類が必要)である父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
- 公務員は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先からの支給となります。
- 原則として児童が国内に居住していることが要件となりますが、例外として「留学」の要件に該当すれば支給されます。留学の要件の詳細については、問い合わせください。
支給額
| 対象児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
|
|---|---|---|
| 3歳未満 | 第1、2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳以上 高校生年代まで | 第1、2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことをいいます
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちら [PDFファイル/323KB]を確認ください。
支給日
偶数月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、金融機関の前営業日が支給日になります。
| 支給月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 6月と7月分 | 8月と9月分 | 10月と11月分 | 12月と1月分 | 2月と3月分 | 4月と5月分 |
手続きの方法
出生・転入などによる請求
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。請求が遅れた場合、支給されない月が発生します。
※15日目が土曜日、日曜日、祝日など閉庁日の場合は、その翌日を15日目として扱います。また、公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。
第1子の出生・転入などの場合
児童手当認定請求書の提出が必要です。請求書はこども政策課または各総合支所にあります。
請求に必要なもの
- 印鑑(本人署名の場合印鑑不要。認印でも可、スタンプ式印鑑は不可)
- 請求者(子どもの父母のうち所得の高い人など)の健康保険証
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し
- 請求者および配偶者の身元の確認ができる書類
請求者(本人)が申請する場合
次の2種類が必要です。
- 番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
- 身元の確認ができる書類
代理人が申請する場合
次の3種類が必要です。
- 請求者の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
- 請求者からの委任状(内容を満たしていれば任意様式でも可)
- 代理人の身元の確認ができる書類
第2子以降の出生などの場合
額改定(増額)請求書の提出が必要です。請求書はこども課または各総合支所にあります。
申請に必要なもの
印鑑(認印でも可、スタンプ式印鑑は不可)
児童手当額改定届(請求書) (PDFファイル/137.21キロバイト)
児童と別居している場合
別居監護申立書の提出が必要です。児童の住所が市外の場合は、別居児童のマイナンバーカードまたは通知カードを提出ください。
児童手当別居監護申立書 (PDFファイル/62.84キロバイト)
大学生年代の子がいる場合
支給対象児童(高校生年代までの子)と、大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を3人以上養育している場合に提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/280KB]
「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページ<外部リンク>
現況届
毎年、監護の状況・所得の状況を確認するために、現況届の提出が必要になります。6月に市から送付される案内を確認のうえ、忘れずに手続きをしてください。手続きをされない場合、6月以降の児童手当の支給が一時保留となりますので注意ください。
他の市町村に転出する場合
他の市町村に住所が変わる場合には、都城市での児童手当の受給資格が消滅します。消滅届を提出してください。
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル/115.45キロバイト)
マイナポータルからも認定請求等が出来ます
平成30年6月1日からマイナンバーカードを用いてオンラインでの認定請求等が可能になりました。詳しくはマイナポータル(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
必要なもの
- 受給者のマイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン(対応機種のみ)