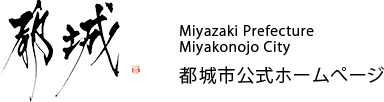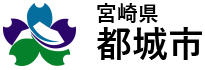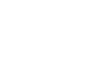本文
【開催終了】令和5年度都城歴史資料館企画展「モノからわかる江戸時代~人々のくらしと産業~」
江戸時代は、現代の私たちのくらしにもつながる新しい町づくりや、様々な産業が盛んに行われていた時代です。当時の都城盆地は鹿児島藩に属しており、現在の都城市域は都城島津氏の領地だけでなく、藩が治める直轄領となった地域もありました。
1615年の一国一城令によって、都城盆地の城はすべて廃城となったことから、都城領主であった北郷忠能は新しく姫城町に領主館をつくりました。同時に武士の屋敷や町場も形成され、領主館を中心とした新しい町が形成されていきます。また、市内各地では様々な産業が行われ、当時の人々の暮らしを支えていたと考えられます。
今回の企画展では、江戸時代をテーマとして、出土品から見えてくる人々の暮らしや様々な産業について紹介します。出土品を通して、江戸時代の暮らしぶりをのぞいてみませんか。
主な展示品
中国象棋の駒(柳川原遺跡:天神町・中町)
新しい町の一つに唐(現在の中国)からやってきた人々が暮らしていた唐人町があります。周辺の発掘調査では中国象棋の駒が出土しており、唐の人々の暮らしが垣間見えます。
天保通宝(中町遺跡:中町)
江戸時代に使われていたお金の一つに、天保通宝があります。江戸時代末期から明治時代にかけて日本で流通しており、形状は小判を意識した楕円形をしています。
三足ハマ(柳川原遺跡:天神町・中町)
三足ハマとは、陶磁器を窯で焼く時に使用する窯道具の一つです。柳川原遺跡では、装飾が施されている珍しい三足ハマが出土しました。
帖佐人形(谷川共同墓地:高崎町前田)
江戸時代のお墓に副葬品として納められていた帖佐人形です。死者の周りを取り囲むように、18体の人形が納められていました。
会場
都城歴史資料館1階資料展示室1
開催期間
令和5年5月19日(金曜日)~11月26日(日曜日)【終了しました】
開館時間
午前9時30分~午後5時(ただし、入館は午後4時30分まで)
休館日
毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は翌日休館)
9月12日(火曜日)・13日(水曜日)は歴史資料館燻蒸のため、臨時休館
入館料
大人:220円(160円)、高校生:160円(110円)、小・中学生:110円(50円)
※括弧内は、20人以上の団体料金
次の場合は入館料無料
- 毎週土曜日は小・中学生
- 毎月第3日曜日(家庭の日)は、高校生以下の子どもがいる家庭や妊娠中の人がいる家庭
- 障がい者手帳を持っている人(介護者含む)
- 子育て応援カードを提示した高校生以下の子どもがいる家庭や妊娠中の人がいる家庭