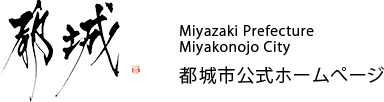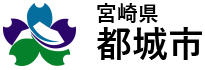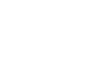本文
都城の歴史と文化財 鎌倉時代~戦国時代
島津荘のおこりと島津氏・北郷氏(都城島津氏)の誕生
「島津荘」のおこり
11世紀の初め、大宰府の官人であった平季基(たいらのすえもと)(参考:神柱宮)が島津駅付近の土地を開墾して、当時の関白・藤原頼通に寄進しました。
この荘園は「島津荘」と呼ばれ、のちに8000町にも及ぶ日本最大の荘園へと成長します。
「島津氏」の始まり
鎌倉時代の初め頃、鎌倉幕府の御家人であった惟宗忠久(これむねただひさ)が島津荘の下司職(のちに惣地頭職)に任命されます(参考:祝吉御所)。忠久は荘園の名をとって姓を「島津」と改めました。これが「島津氏」の始まりです。
「北郷氏(都城島津氏)」の始まり
室町時代の初め頃、島津宗家4代目の忠宗の子・資忠(すけただ)(参考:薩摩迫・山久院跡など)が北郷300町を与えられ、地名をとって「北郷(ほんごう)」と改姓しました。これが「北郷(のちの都城島津)氏」(参考:都城島津家伝来史料・都城島津家墓地・釣こう院跡など)の始まりです。
しかし、このころの北郷氏の勢力は弱く、しばらくは宮丸・和田・高木氏などの有力豪族との争いが続きました。
「北郷氏」の発展
北郷氏は中世城郭「都城」(都島町城山公園)を拠点として勢力拡大を目指し(参考:都城の城跡・安永城・梅北城・高城・山田城・山之口城など)、8代目の北郷忠相(ただすけ)(参考:天長寺の石仏群・伊東塚・不動寺馬場など)の時代、都城盆地をほぼ統一します。
また、同じ時期に北郷忠相の長子・忠親が豊州家(飫肥)を継承したこともあって、北郷氏は南九州東部(現在の都城盆地の1市5町に加え、鹿児島県の末吉町・財部町・大隅町・国分市の一部)を抑える強固な勢力を確立しました。
「庄内の乱」と都城
10代目の北郷時久(参考:兼喜神社社殿)の時代、島津氏は天下統一を目指す豊臣秀吉の前に敗れます。その後の太閤検地や家臣団の所領替えにより北郷氏は祁答院(けどういん)(鹿児島県宮之城町)へ移り、伊集院氏が都城へと入りました。
慶長4年(1599)、島津氏とその家臣伊集院氏との争い「庄内の乱」(参考:志和池城・野々美谷城・森田御陣跡・中原中常坊の墓・長谷原の墓など)がおこり、都城は戦場となりました。
この乱の後、北郷氏は都城へと戻りますが、領地は約半分となりました。また、藩からの命令により姓も「北郷」から「島津」へと改められ、「都城島津」と呼ばれるようになり、島津氏の家来として都城を治めることになりました。